奥の細道 第12の段「須賀川」 宿駅長かつ俳人 相楽伊左衛門宅跡である。
現在は表示のみ残り、栗の木も今日は空曇りなので、物影を映さない。
奥の細道の旅では白河を経て矢吹に宿泊した後、こちらに8日間滞在している。
相楽伊左衛門の俳号は”等躬”であるが、奥の細道では”等窮”と記されている。
これは、”躬”から派生した「極める」意味のある”窮”に尊敬の意味で書き換えているようである。
(以下奥の細道に準じて”等窮”と記す)等窮もは芭蕉よりも年上で俳句の系統(例えば同じ絵画でも抽象画と写実画が違うように、同じ仏教でも臨済宗と曹洞宗が違うように)は違うが、俳人としては先輩であり、以前から交流があったようである。
奥の細道のこの段は劇的な設定及び展開と読む。
普通に読むと、この段は「白河の関」自体の句を詠んだように感じられないが、誤解を恐れず仮説を立て解釈すると、この段は前の”白河の関”(第11の段)を”お題”とした問答である。
地元の等窮は白河の関の現状を知っている。
芭蕉は初めて訪れる白川の関が面影すら残していないことを知る。
本文にある等窮の「白河(第11の段の”白川”でなく”白河”になっていることに着目)の関いかにこえつるや」は、芭蕉に「”不易流行”(簡略に補足すると”不易”は不変の芸術の価値、”流行”は時代や環境や方法に影響を受けて表現が異なるということ)の理念に従い、なにもない白河の関で何を詠む」との問いである。
前の”白河の関”では芭蕉は句を詠んでいない、加えて奥の細道本文でも「旅心定まりぬ」と「雪にも超ゆる心地ぞする」のみが私情として書かれているだけである。
「須賀川」では目に映る地名(阿武隈川、磐梯山<会津根>、岩城、相馬、三春、那須連峰を列挙する。
いわばこれは現実の世界。
つづけて「かげ沼と云ふ所を行くに、今日(けふ)は空曇りて物影うつらず」とあり、”かげ沼”が重要語句と仮説する。
”かげ沼”は「行囊抄」江間氏親著に登場する”逃げ水”のなかに表れる蜃気楼である。
いわばこれは幻の世界。
すなわち、「空が曇っていたのでかげ沼(白川の関を暗示)をみることができなかった」と読む。
加えれば古人の歌にある白川の関は蜃気楼の中に存在する。
ただ、運悪く曇っていたため見ることができなかった ということかもしれない。
ここで詠んだ句「風流の 初めや奥の 田植うた」は、上記の仮説を踏まえると、「(東北地方の)田植えは弥生時代から毎年継続して行われている。
そこで根付いた唄は時代や環境や方法に影響を受けて表現され風流である。
一方、役目を終えた白川の関は在りし日に歌が詠まれたが、実体が伴うものでなく、風流のみが残っている」と読む。
仮説が正しいとすれば、等窮の問いに対して見事な回答である。
ふと、過去の映像が蘇る。
これは、ジョン・スタージェス監督が撮った「OK牧場の決斗」(昔ガッツ石松さんがよく言っていた映画です)を思い起こさせる場面である。
バートはビリーに「早撃ちが自慢か。
早撃ちで35歳まで生きた奴はいないぞ。
自分より早撃ちの奴が現れて、そいつに勝負を挑まれる」といった。
やがてバートはビリーを撃たねばならなくなるが、映画とは逆で芭蕉が等窮を返り討ちすることになる。
(余計なことを書くが、ある天才作詞家が小説でF1パイロットにこの言葉を引用したら本当に35歳より前に事故死してしまった。
手前はそのF1パイロットの追弔よりも、作詞家の心情を慮る方が胸が痛んだ)もう一つの句「世の人の 見つけぬ花や 軒の栗」俳句には季語が必要な”きまり”なので、有力な解釈として「栗の花」で”夏”とされているが、栗の花は特有の強香である。
これを「見つけぬ花」とするのは些か矛盾を感じる。
強引であるが、手前が訳すとすればこうである。
「俗世を離れ栗の木陰に住む僧侶ならば、一般の人には見られない花(在りし日の白川の関を暗示)を見ることができるのであろうか。
」とても見応えのある段であり、併せて余計なものが無く、看板だけ残るこの地に思いを馳せ、ひときわ感慨も深い。
<補足>「奥の細道」の足跡に沿って第1の段から第12の段まで口コミを続けてきましたが、実際訪れたのはここ「須賀川」までで、投稿時点では、この後は、「小松」「山中温泉」「永平寺」にしか訪れていません。
「奥の細道」(素龍清書本)と「曾良旅日記」と地図があるので、続きを書くことは可能でありますが、反面、訪れたことも無いのに口コミを書くのは如何なものかとも考えます。
将来訪れるか、もしくは一連の投稿に反響が大きかったら継続したいと考えております。
次の機会がありましたら、特異な口コミでありますが、目を通して頂けますと幸甚です。
| 名前 |
相楽等躬屋敷跡 |
|---|---|
| ジャンル |
|
| 住所 |
|
| 評価 |
3.0 |
周辺のオススメ
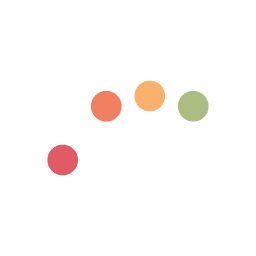
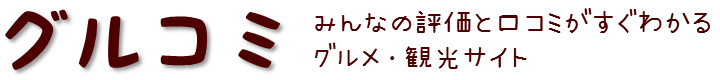
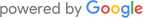
素晴らしい景観!桜の季節に来てみたい!